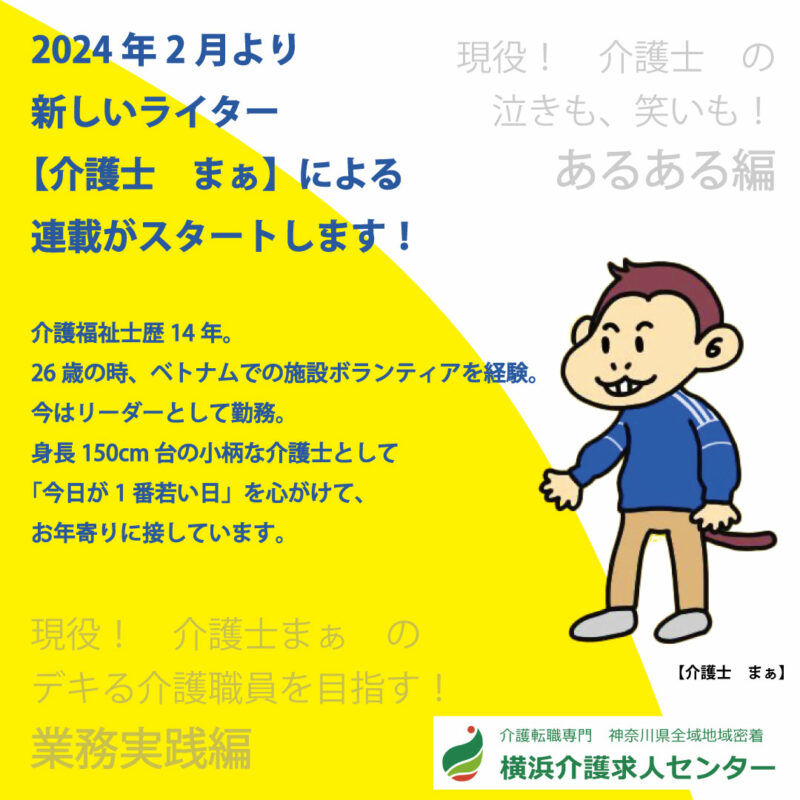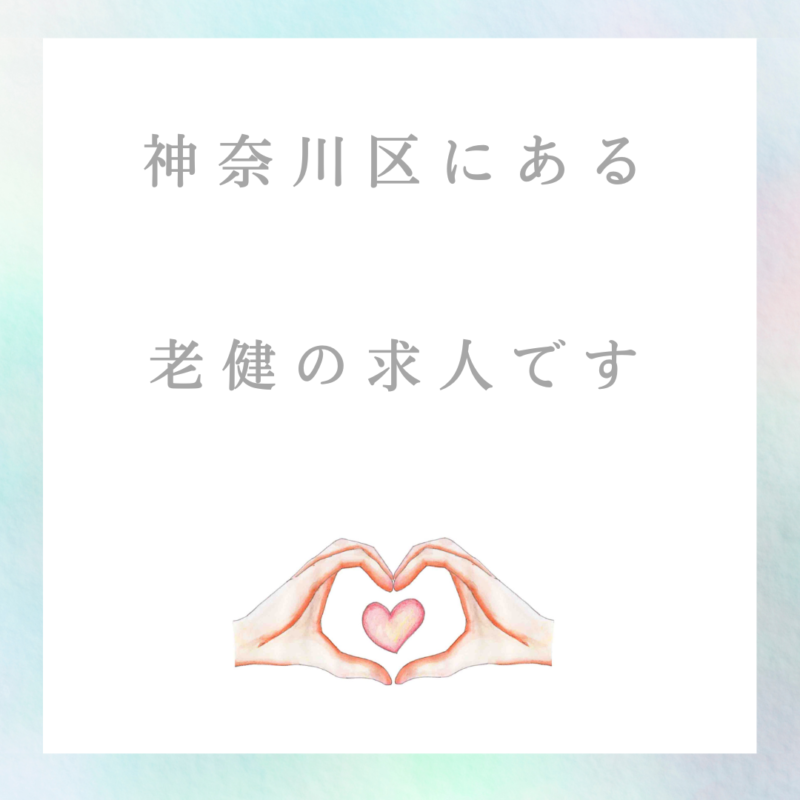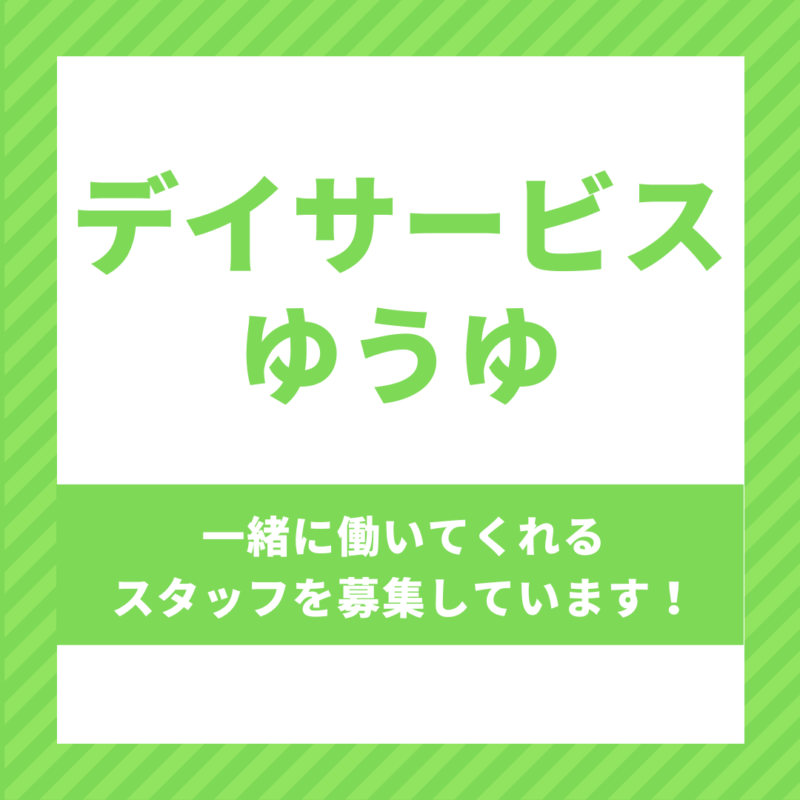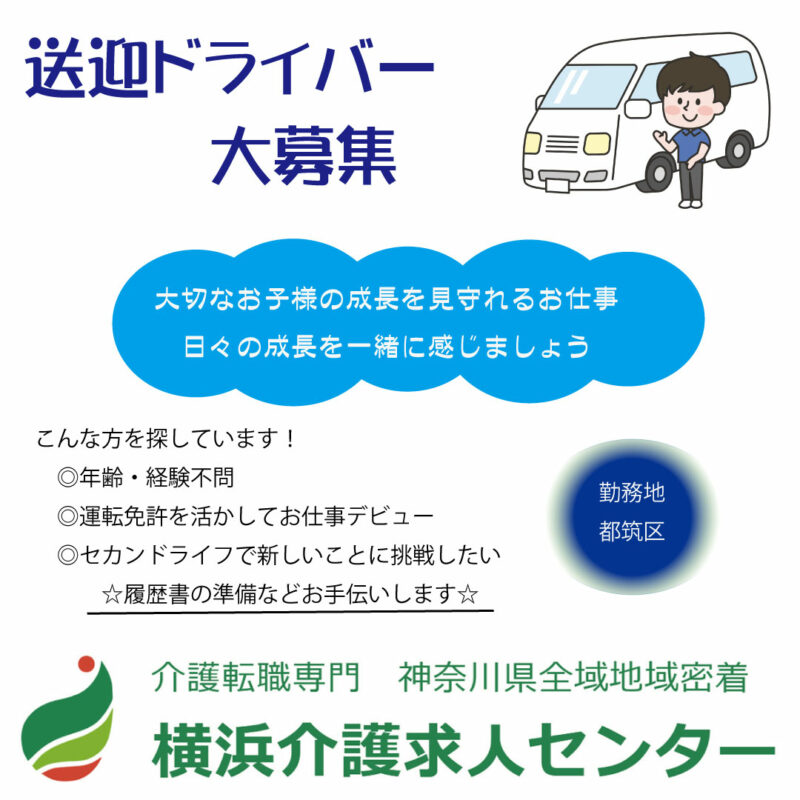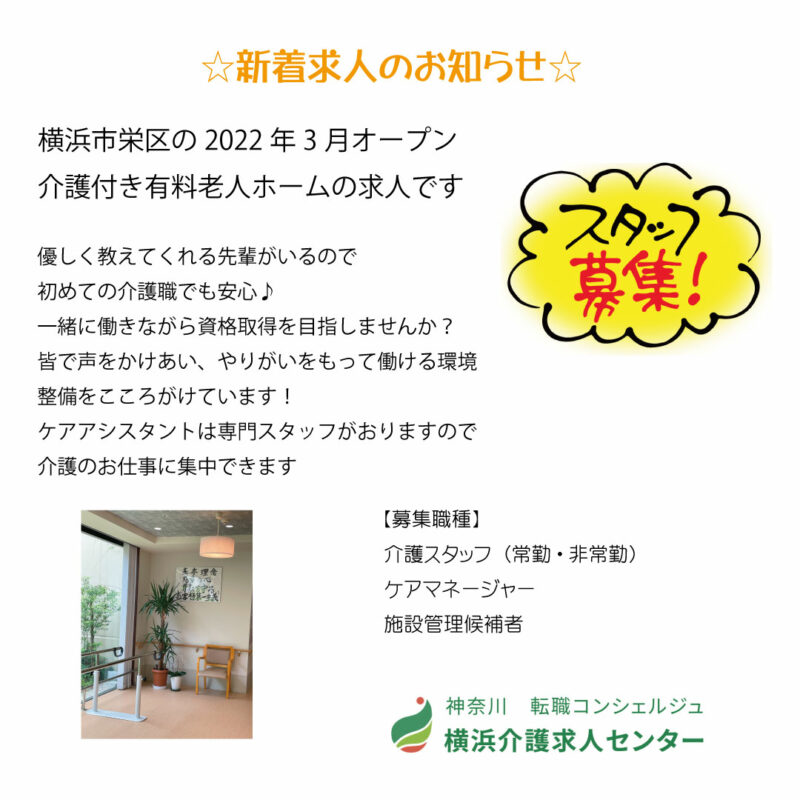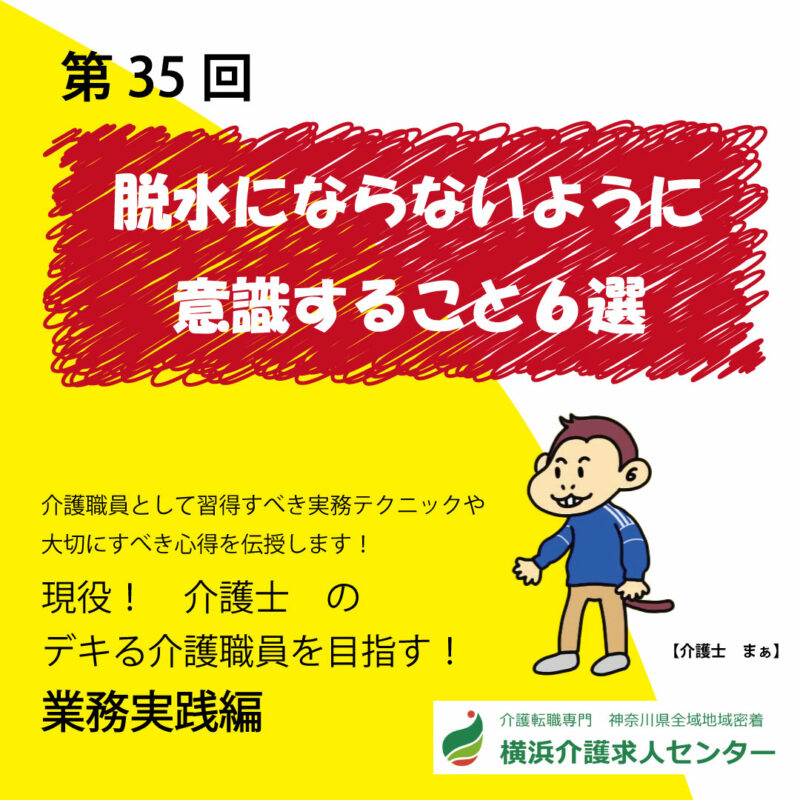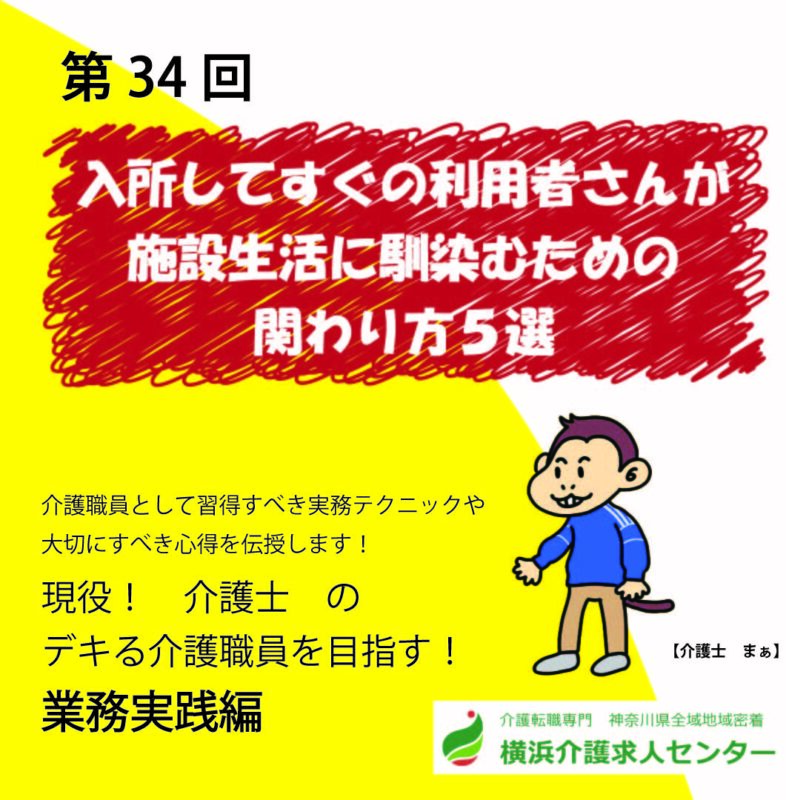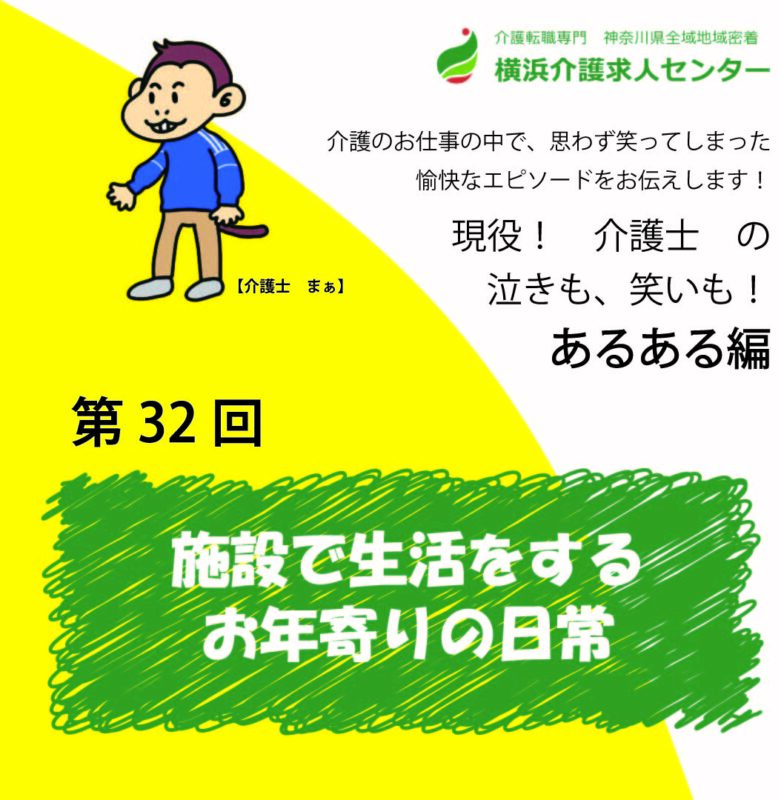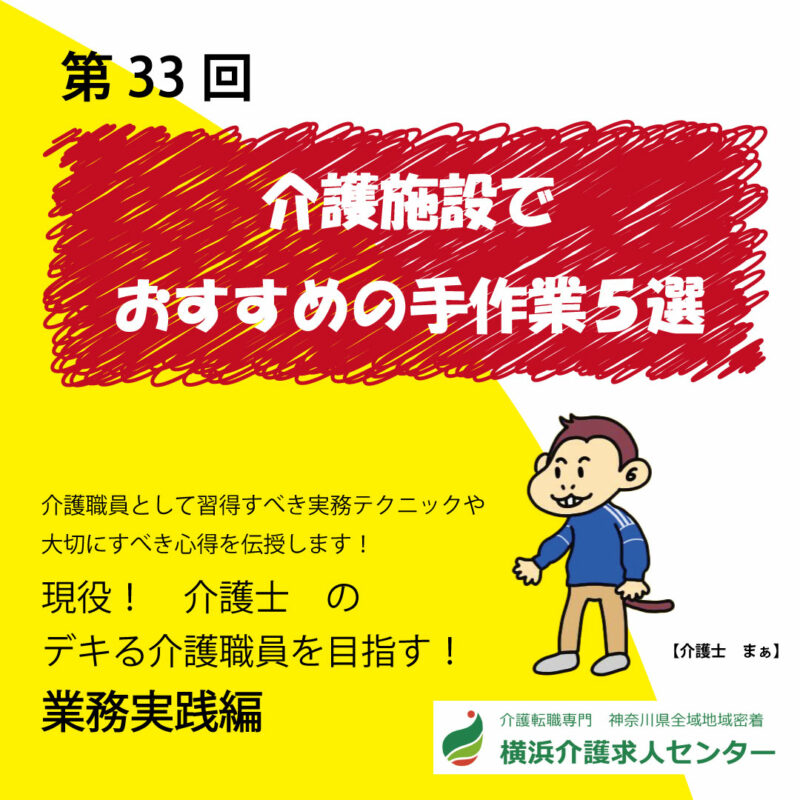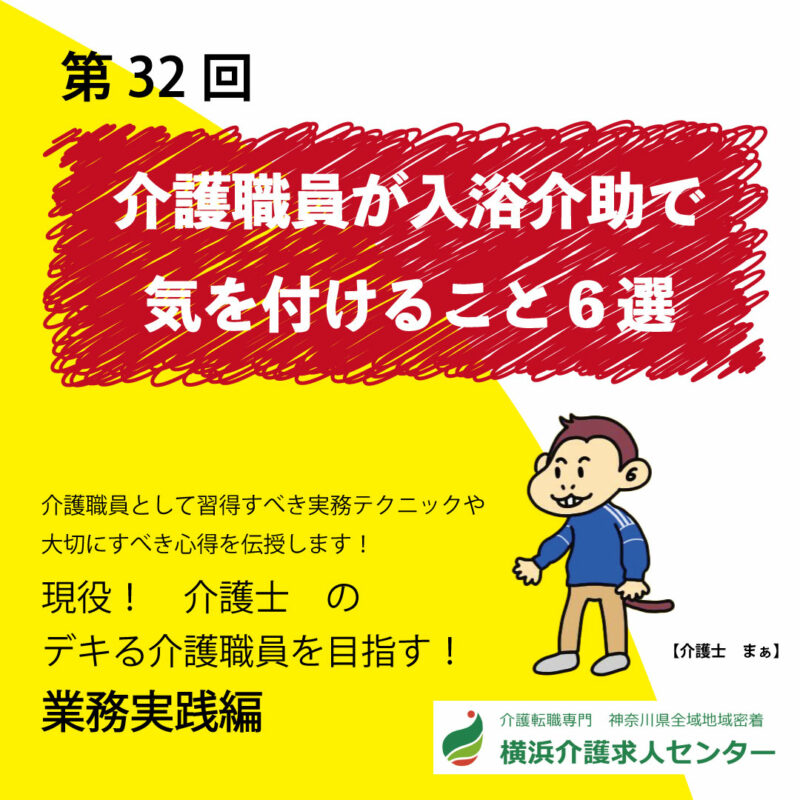がんばりすぎない
『横浜介護求人センター』
第35回「脱水にならないように意識すること6選」
・脱水になると、どのような体の変化が起こるのか
脱水や熱中症で倒れる方のニュースはよくテレビで取り上げられていると思います。気をつけて水分を取らないと いけないとわかっていても、高齢になると喉の乾きを感じにくくなったり、「トイレが近くなる。焦ってトイレに 行きたくない。たくさん飲んだら漏らしてしまうんじゃないか」と不安になり、水分を控える方もいらっしゃると 思います。しかし、体内の水分が減少すると『イライラする、ウトウトする、ぼーっとする、落ち着かない』という 意識障害が起こることもあります。そして、さらに体内の水分量が減少すると、発熱したり、運動機能の低下に つながります。食欲不振になったり、疲労感やめまい頭痛が起こる。ひどくなれば幻覚が生じたり、意識を失う、 死亡する可能性もあります。
・1日にどれくらいの水分摂取が必要なのか
人間が1日に必要な水分量は体重1Kgにつき35ml〜40mlが必要だと言われています。例えば、体重が50kgの方の場合は、 1700ml〜2000ml摂取する必要があります。そのうちの半分ほどは食事(お米、味噌汁、野菜など)から摂取しています。 そのため、飲んで補給する水分は1日1000から1500mlと言われています。 (人それぞれ体重や食事量が違うため大体の目安になります)
・利用者さんの体型に合わせた水分摂取をしたことによって起こった変化
夕方になると荷物をまとめて玄関に歩いて行かれ「帰るから玄関を開けてほしい」と、不安を訴えられる方が いらっしゃったのですが、水分摂取がしっかりとできている日は、落ち着かれ帰宅願望が無くなりました。 その他にも、パッド内に失禁されていた方が、パッドが汚れる前にトイレにご自身で向かわれるように なりました。ウトウトと傾眠が目立つ方や、ずっと目を瞑っておられて方が、目をぱっちり開けておられたり、 食事の際に介助や声かけが必要だった方が、ご自身で召し上がれる時間が増えました。 排便での変化もあり、下剤を使用しておられる方の使用頻度や、使用量が減りました。 血液検査の結果にも少し変化があり、脱水状態で血液検査をすることで血液が濃くなっていることで、本来の値より それぞれ高い数値になることもあるそうです。つまり、本当はもっと低い数値だということです。血液検査の結果も 脱水状態で検査すると異常が確認できないこともあるんです。利用者さんの中にはアルブミンという値が 少し低下した方もいらっしゃいました。その方は、すぐに何か対応が必要というほど、値が低いわけでは ありませんでしたが、脱水によって血液検査の結果も変化するということには驚きました。 全てが水分摂取量を増やしたことだけが要因ではないと思いますが、このような変化が見られました。
「少しずつ摂取する」
水分摂取量が少なく、脱水になる可能性のある利用者さんがおられました。1日でどれだけ飲んでおられたかチェックをしたり、 スタッフも意識して声をかけたりしていたのですが、ご自身から水分を飲むことはされず、1日600ml飲めるか飲めないかぐらいの 摂取量で、声かけを行うと少し飲んでくださる方でした。小柄な方だったこともあり、1日1000mlを目標に少しづつ飲んでいただいて いました。あまりにもしつこく声をかけると、怒ってしまい全く飲んでくださらなくなるため、時間を空けて声かけをし、 毎日続けることで、少しずつ飲む量も増えていき、1000mi前後飲んでくださるようになりました。すると以前に比べて、発語も増えて、 目もぱっちりと開けてくださり、笑って冗談を言ってくださり、食事量も増えていました。水分量が少なかったことだけが理由だった 訳ではないと思いますが、脱水傾向にあったのも原因の1つだったんじゃないかなと思っています。 夏になると、脱水症状で入院される利用者さんが増えるんです。水分量を気にしていれば脱水になることはないと思うのですが、 喉の渇きを感じられなかったり、トイレにいく回数が増えるのが嫌だったりと、水分摂取量が少なくなる方は必ずおられると思います。 一気にたくさんの水分を飲んでしまうと身体に吸収しきれなかったり、排尿回数が増えてしまうので、飲みたくなくなるお年寄りの方は 多いんじゃないかなと思います。そして、高齢になると喉の渇きを感じにくくなるため、意識して水分を摂らないと、摂取量が少なく なってしまいます。そのため、目安としては1〜2時間おきにコップ1杯分を摂取するといいと思います。例えば、起床時、昼食前、 昼食時、おやつ時、夕食前、夕食時にコップ1杯(200ml)を摂取すると1200mlになり、お薬を服用されている方なら1500mlぐらいは 摂取できるのではないでしょうか。1回に200mlも飲めない方は、もっとこまめに分けて、少しずつ飲んでいただいてもいいと思います。 だからといってたくさん飲まないといけないからと、短時間に大量の水分を取ると、水中毒になる恐れもあるので、気をつけないと いけません。
「好きなもので摂取する」
お茶やコーヒーが苦手な利用者さんでしたが、ご家族とお話したり、ご本人さんに好きな飲み物を伺ったりしていくうちに 冷たいお水や牛乳がお好きなことがわかりました。そこからは、食事の際はお茶を提供して、食後に冷たいお水を提供したり、 朝食がパンの日には、紅茶やコーヒーではなく牛乳を提供するなど、お好きな飲み物を提供することにしました。その際、担当の お医者さんにも糖質や脂質などが他の飲み物より多くなってしまうので、確認して許可を取ったり、日常的に飲んでいることを 伝えることで、変化があった時には、気づいていただけやすくなったと思います。そして、主治医に伝えていることで、 ご家族さんにも安心していただけたと思います。水分摂取量が増えたからなのか、環境がご本人さんに会っていたのかは わかりませんが、うつ傾向にあり、薬を服用されていた利用者さんでしたが、今では抗うつ剤を飲むこともなく、穏やかに 生活を送っておられます。 水分摂取が苦手な方に、無理なく進んで水分摂取してただけるようにするためには、好きな飲み物を把握することが 大切なんじゃないかなと思います。いろいろな飲み物を揃えて置いておいてもいいだろうし、ご家族様に個人用で持って来て いただいても、いいんじゃないかなと思っています。昆布茶やミルクティーなどを置いておいたり、普段提供しているお茶の種類を 変えたり、増やしたりして飽きないように工夫するのもいいんじゃないかなと思います。 水分をとってほしいけど、喉が渇いていなかったり、飲みたい気分じゃないと促しにくいと思います。好きなものなら飲んで いただけるなら好きなものを提供する方法もあると思います。その時は主治医の先生と相談して、糖尿病がないか、どれぐらいなら 飲んでも良いのかを確認したり、ご家族さんの協力も得ながら脱水にならないように気をつけていきたいと思います。
「ゼリーで摂取する」
水分摂取が苦手だったり、水分でむせてしまうけど、固形物は飲み込むことはできる方がいらっしゃいました。そんな方たちの 水分摂取は、ゼリーでの提供をしています。トロミをつけた水分の提供もしますが、ゼリーの方が食べてくださる方でした。いろんな 飲み物を提供するだけでなく、利用者さん1人ひとりにあった水分摂取の方法を考えて、食感や、喉越しの違うものを提供することで 飽きることなく、利用者さんも進んで水分を摂取してくださいます。大きめの容器にゼリーを作って冷やしておけば、すぐに提供することもできて、便利だと思います。利用者さんからの人気もありゼリーを召し上がっている利用者さんをみて「美味しそうやねぇ。私も ちょうだい」とゼリーを希望される方もおられます。生クリームを乗せたり、トッピングをすることで、おやつの時や、食事のデザート としても提供することができます。水分補給だけでなく、豆乳寒天にすると、タンパク質も摂取することができます。 水分を飲むことが苦手な方はいらっしゃいますが、ゼリーなどの喉越しがよく、あっさりしたものなら召し上がってくださることが あります。ジュースとゼラチンとお湯で簡単に作ることができますので、ぜひ試してみてください。
「環境を変える」
食事の際に提供した水分を飲み切ることができずに、残されてしまう方がいらっしゃいました。食後にも少し飲んでくださって いましたが、全て飲み切ることができませんでした。そこで、一度、食後の口腔ケアにお連れし、戻ってきてから飲んでいただいたり、 食後にリビングでテレビを見ておられる際に「お茶入れましたよ」と提供したり、利用者さん同士でお話しされている時に提供したり、 居室に戻られてゆっくりされる際に、水分をお持ちして提供させていただいたりと、居場所が変わった時にお声かけして、提供する ことでまた飲んでくださるようになるんです。一度違うことをすることで、気持ちを切り替えることができるためなのか、水分を摂って くださる方が多いです。テレビを見ながらだったり、ご自身のお部屋で落ち着いてゆっくりできる空間だと、飲めるようで、声かけを しなくても環境や場所を変えるだけで水分を摂取してくださる方もいらっしゃいました。お一人おひとりにあった環境を見つけることで、 自然と水分摂取が進むのかもしれません。あとは、利用者さんと一緒にお話ししながら一緒に飲んだり、飲み始めるきっかけに なるように乾杯をして自分が先にお茶を飲んだりして、飲んでいただけるように促すこともしています。
「運動をした後に摂取する」
水分をあまり取られない方は結構いらっしゃいます。「トイレが近くなるから…」と断られる方もいらっしゃいます。 そんな方には、その方にあった活動を行っていただいたり、体操の後などにこまめに提供するようにしています。 コップにたくさん入れてしまうと「こんなに沢山飲めない」とおっしゃるので、50〜100mlぐらいをコップに入れて 体操の後、おしぼりを畳んでいただいた後、散歩や日向ぼっこの後など何かする前や後に少しずつ声をかけるようにしました。 すると、少しの量を何回にも分けて、しっかりと水分をとってくださるようになりました。 何か、飲むきっかけがあったり、次の動作へ移る前に飲んでいただくというのも効果的かもしれません。その取り組みは、 体操、洗濯物干し、散歩、おしぼりたたみ、調理、入浴など活動の前後で声かけを行うことです。活動の前より後の方が、水分を とってくださることが多いです。「体を動かした後なので、しっかり水分を摂っておいてくださいね」や「汗をかいたと思うので 喉が乾く前に、少しでもいいので何か飲みませんか?」などと声をかけると、自然と水分を摂ってくださると思います。
「利用者さんにお茶を淹れていただく」
お茶をお出ししても、なかなか進まない方は多いと思います。そんな時に、ご自身でお茶を入れていただいたら 美味しく感じるのではないか、自分が入れたお茶を「おいしいね」と他の利用者さんやスタッフに飲んでも らえることで、やりがいにもつながり、周りの人が飲んでくれるなら、自分も飲もうかなと思うんじゃないかという 話になり、しばらく試すことにしました。すると、急に飲んでくださるようになったということではありません でしたが、少しずつ飲む量が増えて、「私が淹れたお茶でおいしいと喜んでもらえて嬉しいわ」と恥ずかしそうに 喜んでおられました。利用者さんの役割りにもなり、とても良い取り組みになりました。 誰かに淹れてもらったお茶もおいしいと思いますが、自分で淹れたお茶はそれ以上に美味しいと思う方も いらっしゃいます。そして、誰かに飲んでもらって「おいしい」と言ってもらえれば、自分でも飲もうと思うようです。 誰かに淹れてもらったお茶もおいしいですが、自分や他の人のために入れたお茶も美味しく感じると思います。 それは、誰かのために何かをすることで、役に立ったと思えるからです。そして、上げ膳据え膳ではなく、 自分のことを、自分でできる喜びもあると思います。
最後に…
夏だけでなく、冬にも脱水になる方はおられます。水分を摂ることだけに気を付けるのでなく、エアコンの温度を調節したり、 扇風機などを使ったりして、室温の調節にも気をつけてください。夏場は特に、暑さを我慢せずに早めにエアコンを 入れるといいと思います。体温調整が難しい方は、厚着をしていないか、薄着になっていないかなど、衣類にも気をかける 必要があると思います。体調には気をつけて、少しでも体調がいつもと違うなと感じた時には、我慢せずに病院に受診することを お勧めします。 最初は、水分を飲む習慣がないと、慣れるまでは、なかなか目標の水分量を飲めないと思います。少しずつ意識するところから 始めて、目標の水分量を飲める日もあれば、飲めない日もありながら目標達成する日が増えたらいいんじゃないかなと思います。 寝る前にたくさん飲んでしまうと、失禁や、トイレの回数が増えてしまうかもしれないので、日中の水分量を増やすことを 意識した方がいいと思います。1度にたくさんの水分を飲んでも、トイレの回数が増えてしまったり、水中毒になる可能性も あるので気をつけて飲んでいただいてください。初めは、どんなものでも好きなものを飲んでいただければいいと思うのですが、 カフェインが入っている飲み物には利尿作用があるため、トイレが近くなってしまいます。カフェインの入っていないオススメの 飲み物は、麦茶、コーン茶、ルイボスティー、胡麻茶、黒豆茶などです。汗をたくさんかいたり、脱水の恐れのある方には、 スポーツドリンクや、昆布茶で塩分とミネラルの補給を行えるといいと思います。ただ、心疾患、腎疾患、高血圧、糖尿病などで 制限のある方もいらっしゃると思いますので、かかりつけのお医者さんに確認して水分摂取を行ってください。 脱水で入院したり、亡くなられる方がいなくなることを願っています。
「いざという時の経口補水液の作り方」
脱水の症状の方がいらっしゃるが、経口補水液がない場合は、水1ℓに砂糖40gと塩3gとレモン汁50mlを混ぜると出来上がるので いつでも作れるように、メモをしておいてくださると便利だと思います。 あくまで、緊急的な対応としてご活用ください。嘔吐や下痢による脱水の場合は、市販の経口補水液をご使用ください。 参考になれば嬉しいです。
(2024年7月1日)
第34回【入所してすぐの利用者さんが施設生活に馴染むための関わり方5選】
「会話の機会を設ける」
入居されてすぐの利用者さんで、お風呂は家で入るからと断っておられる方がいらっしゃいました。トイレのお声かけをしても断って おられ、衣類が汚れて気持ち悪いから仕方なくトイレに向かわれるという方でした。スタッフに介入されるのを拒まれて「自分で するからほっといて!」と初めはおっしゃっていました。そして、夕方になると「今から帰ります」とカバンを持って、玄関の前で お迎えが来るのを待っておられたりもしました。そんな方でしたがお話しするのがお好きで、他の利用者さんとの会話も楽しまれたり、 スタッフが話しかけると笑顔でお話をしてくださり、手作業にも快く答えてくださる方でした。スタッフが根気強く話しかけて、関係性を 築いていくことで、少しずつ介入させていただけることが増えました。何回かに一回は、トイレに行ってくださったり、 お風呂の声掛けにも、着替えだけはさせていただけるところから始まり、足湯だけならしてくださるようになり、体を洗うだけ、湯船に 浸かるだけの日が増えていき、最終的には洗髪、洗身、入浴までしてくださる日が徐々に増えていきました。利用者さんが安心できる 場所にするまでには、スタッフとの関係性も大切で、1日でも早く施設での生活に馴染んでいただくためには、意識して話しかけ、 安心できる存在になることが大切だと学びました。 お話好きで、ご自身から誰にでも話しかけることのできる方もいらっしゃいますが、そうではない方もいらっしゃると思います。 入所されてすぐには、自分から話しかけるのは、勇気がいるし緊張すると思います。誰かわからない方には警戒される方もいらっしゃい ます。スタッフの方からたくさん話しかけることで「ここにいていいんだ。この人は話しかけてくれる人だ」と安心していただける存在に になることが大切だと思います。そのためには、毎日、少しでもお話しする機会を作り、話した内容を覚えて、その利用者さんの好き話、 盛り上がる話題を選ぶことも必要だと思います。事前に利用者さんの情報がわかるのであれば、個人情報に目を通しておくことで、 どんな話をしようか、そんな話はこちらからしない方が良いのかも考えられると思います。
「意識してお名前を呼ぶ」
入居されて間もない利用者様がいらっしゃいました。初めは、不安そうにされてキョロキョロ周りを見渡したり、近くに座っておられる、 他の利用者さんに会釈したりされていました。そんな時に、入居された利用者さんのお名前を他の利用者さんにお伝えしたり、その日の 予定や次に何をするのかをお伝えする時に、お名前を呼んでお声かけして伝えたり、お名前を呼んで「大丈夫ですか?」と声をかけたり するように心がけていました。すると、何か不安なことや、気になることがあれば声をかけていただけるようになり、笑って くださったり、出勤すると1番に声をかけてくださったりと、徐々に心を開いてくださることがありました。介護施設で働いていると、 新しく入居される方と出会う機会があると思います。スタッフは、何度も経験することでも利用者さんからすれば、初めてのことです。 施設に入所されてすぐは、知っている人がおらず、自分のことを知ってくれている人もおらず、不安でいっぱいだと思います。 そんな時に、利用者さんのお名前を意識して呼ぶことで、安心感に繋がると思います。中には、結婚して苗字が変わっている方の中には、 自分のことだと認識されていない方もいらっしゃるかもしれませが、そんな時は、周りからどのように呼ばれておられたのかを、ご家族に 確認して呼び方を変えてみることも必要かもしれません。相手やご家族が不快になる呼び方ではなく、利用者さんが、自分のことを 呼んでいると認識できて、安心できる呼び方をご家族や利用者さんを取り巻くいろいろな方と相談し統一することで、混乱することも なくなるのではないかと思います。名前は昔から呼ばれ続けて、自分だと認識できるものの一つなので、呼ばれることで自分のことを 知ってくれている存在がいるんだと思えて、心地よさや、安心感を与えることができると思うんです。僕自身、入社してすぐの時は 、1人で不安だった時に先輩方に名前を呼んでもらったり、声をかけてもらってホッとした経験があります。その安心感はいくつに なっても同じだと思います。
「他の利用者さんと手作業の時間をつくる」
新しく入居された方は家事が得意な方でした。手持ち無沙汰や初めての場所での不安や緊張からソワソワしておられ、初めは周りの 利用者さんの様子を伺っておられました。洗濯物を干す時に、その利用者さんと、普段からよく洗濯物を干してくださる利用者さんに 声をかけて一緒に行っていただきました。初めは2人で黙々と干しておられたのですが、スタッフが間に入り、お互いの紹介をしながら 3人で話をしながら洗濯物を干していました。作業後は、3人でお茶を飲みながら会話の続きを行うと、緊張されていた利用者さんからは 笑顔も見られ、少し不安が和らいだ表情をされていました。誰でも関係性ができるまでは、話題がないと誰かと一緒にいるのは気まずく なるんじゃないかと思います。一緒に作業をすることで、協力して手作業をすることができます。そして、やり方を教えたり、 教えてもらったりして助けあい「ありがとう」とお礼を伝えることで、話しやすい関係性ができるきっかけになり、自然と会話をする きっかけになるんじゃないかなと思います。ただ、入居されてすぐの利用者さんの身体機能などがわからないと逆にトラブルになったり、 自尊心を傷つけてしまうことにもなるので、どんなことができるのか、何が得意なのかを事前にご家族に確認したり、利用者さんの 日頃の様子から、どんなことができそうかを観察し、会話の中で情報収集することが大切だと思います。初めは「失敗したらどうしよう、 やり方を間違えて、恥ずかしい思いをしたくない」という思いから、拒まれることもあると思いますが、そんな時はスタッフと1対1から 初めて、自信がついたら他の利用者さんと一緒に行うようにしても良いんじゃないかなと思います。
「お礼を伝える」
入居された日から、かばんを手放すことなく抱えて持っておられました。そして、夕方になれば「帰ります。玄関開けてください」と おっしゃる、帰宅欲求のある利用者さんでした。常にカバンを持っておられたので、スタッフ同士でどうしてカバンを居室や、お席に 置いたりされないんだろうか。という話し合いを行いました。その話し合いの中には、必要なものを持ち歩くため、そのかばんを大切に されていて無くしてはいけないからなどの意見もありましたが、いつでも帰れるように準備している。安心できるものを持っていたいから ではないのかという意見もありました。きっと、安心できる空間ではなく不安や緊張が強かったり、安心できる場所に帰りたいという 思いから、かばんを手放さずに持っておられるんじゃないのかなという結論になりました。そして大切に抱えておられるかばんを置かれた その時は、少し不安が取れたんじゃないかなと考えることにしました。その際に、荷物を置いておいてくださいとは伝えずに、 ご本人さんの意志でかばんをおいてくださるのを待ちました。その時に行った方法は、利用者さんにお礼を伝えられるように関わること でした。その方ができることを探したり、小さなことでも、何かお願いできることを探してその都度、お礼を伝えました。他の利用者さん と一緒にできる手作業の時もそうですが、例えば、台車を使って食器を厨房に運んでいただいたり、おしぼりを畳んでいただいたり、 テーブルを拭いていただいたりした後に「ありがとうございました。助かりました。またよろしくお願いします」などの声をかけるように しました。お礼を言われて嫌な思いをする人は、ほとんどいないと思います。誰かの役に立っている、自分には役割があると感じ、 存在意義を感じられると、ここにいて良いんだと思えるんじゃないかなと思います。そうすると居場所につながって、安心できる空間に なるんじゃないかなと思います。何もしたくないという方もいらっしゃると思うので、初めはその方の居場所作りのきっかけのために、 試してみるのもいいと思います。初めは良くても、だんだんと重荷になる方もいらっしゃると思うので、利用者さんのプレッシャーに ならない程度のお願いから始めてみると良いんじゃないかなと思います。そして、徐々にお一人おひとりにあったことや得意なことを お願いすることができれば、もっとその利用者さんだけの役割になり、存在意義が出るんじゃないかなと思います。かばんを肌身離さず 持っておられた利用者さんは、お願い事をして行ってくださる時は、荷物を下ろしてくださるようになり、お礼を伝えることを続ける ことで、徐々にかばんを持たれなくなりました。今では、ほとんどかばんを持ち歩かれなくなり、かばんを持っていると時は、 不安な時じゃないかなと思って接するようになり、その利用者さんの精神的なバロメーターとしても見られるようになりました。
「散歩に出かける」
認知症の症状のある利用者さんで、自宅でもお一人で外出されることは無かったのですが、体力に自信があり、入居することで活動量が 減ったように感じておられました。じっとしていることが苦手な方でした。話しかけられると、お話もされるのですが、ご自身から 話しかけられることは、あまりありませんでした。そこで、ご本人さんの希望で散歩を日課にしました。すると、散歩をしながら 入居するまではどんな生活をしていたか、体力に自信があって、どんな幼少期を過ごして、どんなことが好きなのかなどどんどん 話してくださるようになり、笑顔も増えていきました。初めは、スタッフと1対1で散歩に出掛けていたのですが、他の利用者さんとも 散歩をする機会を作ることで、お互いの話をしながら歩かれて利用者さん同士の関係をつくるきっかけになりました。 施設の中だけでの生活では、息が詰まる思いをする方もいらっしゃるかもしれません。少し外に出るだけで、閉鎖された空間から 出ると、開放的な気持ちになり、話しやすくなるんじゃないかなと思います。大人数の中での会話は混乱されたり、緊張して話しかけ にくいことやもありますが、少人数で会話することで話しやすい環境を、つくることができたんじゃないのかなと思います。 入居されてすぐの利用者さんだけでなく、普段から散歩に出かけることで、いろいろなお話ができて、新たな発見ができたり、 利用者さんとの関係が深まるきっかけになるんじゃないかなと思います。運動はストレス発散にもなり、体力の維持や向上、健康の ためにも続けていきたいなと思います。
最後に入居を検討されているご家族様へ、、、
入居されてすぐの利用者さんのご家族にはできるだけ面会に来てほしいと思います。「頻繁に会いに行くと施設での生活環境に順応 しにくくなるんじゃないのか。別れ際寂しくなって、余計に辛い想いをさせてしまうんじゃないのか」と考える方もいらっしゃると 思いますが個人的には環境の変化をできるだけ緩やかにするためにも、急に全く知らない環境に1人で飛び込むよりは、安心できる 家族という存在が、同じ空間にいることで、少し緊張も解れるんじゃないかなと考えています。それぞれの施設の考え方や、入居される 利用者さんの性格などもあると思いますので、入居される時に、施設の管理者さんと施設の生活に馴染むまでにどうしていけばいいかを 相談することをお勧めします。個人的には、初めは知らない人ばかりの中で生活することになるので、ご本人が施設での生活に慣れる までは安心できる存在のご家族が会いに来てくださることで、利用者さんは安心できると思っています。
(2024年6月4日)
第32回【施設で生活をするお年寄りの日常】
「お風呂が苦手な利用者さん」
普段は、歌の番組や、お笑い番組が大好きでよく笑っておられる利用者さんがいらっしゃいました。しかし、 お風呂の声かけにはあまりいい顔をされませんでした。声かけをするスタッフを代えて声かけしてみたり、 何かに集中されている時には声をかけずに、タイミングを見計らって声かけしたりもしていたのですが、断られることが 続きました。そこで、その利用者さんのよく口ずさんでおられる歌を一緒に歌いながらお風呂にお誘いすることにしました。 すると「お風呂いこか」と笑って浴室まで向かってくださり、ご自身で衣類を脱いでくださり、進んで入浴してくださるように なりました。色んな利用者さんがおられて、断られることもたくさんありますが、1人ひとりにあった対応を見つけられることで こんなにも、断られることがなくなるのかと驚きました。浴槽内でもずっと歌を歌っておられます。
「観梅」
いつも、施設の廊下でも慎重にゆっくりと歩かれる利用者さんがおられました。「外には出かけたいけど、しんどくなったら嫌だし、 外を歩くのも怖いな」とよくおっしゃっていました。しかし、暖かくなり、施設の近くに綺麗な梅が咲いていると言うニュースを見て 「綺麗やな。見に行きたいな」と他の利用者さんとお話しされていました。なかなか外に出たいと話されることがなかったので、 気持ちが変わらないように、その日に梅を見に行くことにしました。普段は杖歩行をされているのですが、ご本人の不安もあり、 念の為、車椅子を持っていきました。到着すると駐車場から見える梅に「わぁ、きれいやね」と喜んでおられました。 車から降りると、車椅子のことは忘れて歩きだされたので、横に付き添って一緒に歩きました。慎重に歩いておられたので、 足元しか見ておられず「どんぐりがいっぱいやねぇ」とおっしゃっておられました。少し立ち止まって見上げていただくようにお伝えすると 「うわぁ。きれいやねぇ」と満開の梅に驚いておられました。「足元ばっかり見ておったから、どんぐりだけ見て帰るとこやったわ」と笑っておられました。 その後も、ゆっくりと歩いては立ち止まり梅を見上げておられました。 最後まで車椅子を使うことなく、ご自身のペースで梅を観て周られました。施設に帰ってからも「どんぐりだけ見て帰るとこやった」と 笑いながらいろんな方にお話しされていました。
「お見送り」
いつもニコニコしておられる、利用者さんがいらっしゃいました。スタッフのことを労ってくださり、自分のことは後回しで 「ご苦労さま。たまには座りや」と声をかけてくださいます。杖歩行で、介助は必要ないのですが、すり足で歩いておられるため歩行時は付き添いの対応をしていました。 仕事を終えた職員が帰ろうとするのを見かけると「もう帰るんか?ちょっとそこまで送るわな」と、お話しながら玄関まで送ってくださる。 「どこまで帰るんや?電車か?家は近いんか?今日は雨降ってなかったかいな?気をつけてな。次はいつくるんや?」と心配がとまらないんです。 お見送りが終わると、別のスタッフが付き添ってフロアに戻っていかれます。 そんないつもスタッフのことを気にかけてくださるとっても優しい利用者さんに癒されています。
「私のおばあちゃん?」
施設の廊下には、イベントなどで撮影した利用者さんの写真を、飾っています。普段は、写真を気にされることのない利用者さんですが、写真を見て、会話のきっかけになることがあります。 ある利用者さんと写真のお話をした時に、写真に写る自分の姿を見て「これは、おばあちゃんや。どんな人かは知らんなぁ」と仰ったり「これはお母さんよ。〇〇に行ったときの写真かしら」とその時の話をしてくださいました。 その後、ご家族にその話をすると、昔の写真を持ってきてくださいました。 そこに写っていた写真のお母さんは利用者さんにそっくりでご家族も「間違っても仕方ないわねぇ」と笑っておられました。その笑っておられるご家族さんと、写真に写る利用者さんもとても似ておられました。
「お月様」
夕食が終わると、いつもソファーでゆっくり過ごされる利用者さんがいらっしゃいました。テレビを観たり、他の利用者さんとお話をして過ごされたりしています。感情を表に出すことはあまりなく、笑う時もお上品に笑う方でした。そんな利用さんの感情が出るタイミングがありました。 それは、お月様が出ている時です。天気や、周りの建物、時間帯によって毎日見られる訳ではないのですが、見つけた時にはお伝えします。 すると「えっどこから見えるの?」と目を丸くしてソファーからすぐに立ち上がられます。 曇りの日でも雲の隙間から見えるお月様を眺めておられました。何より満月の日を楽しみにされていて、満月の日が近づくと「明日は満月かな。 見られたらいいわね」とお話しされていました。 そして、満月が出た日にお月様が見られるとご家族に電話をかけ「今ね、お月様を見せていただいたの。今日は満月よ。そっちからも見える?」とお話しされます。 いつ満月が出るのか把握するために、月齢カレンダーを用意しました。毎日、カレンダーを見て、今日のお月様と次はいつ満月が出るのかという話をして楽しみにしておられました。
「指相撲」
100歳を超える利用者さんがいらっしゃいました。発語もあまり多くなく、小さい声で話されます。コミュニケーションも難しく、 表情を読み取ることが難しかったのですが、握手をするように手を繋ごうとすると、なぜか指相撲をする形に手を組まれます。 そして、スタッフの親指を押さえようとされるんです。思った以上に力が強く、長い指で不意に押さえられるので指を戻すことができないんです。 利用者さんの顔を見ると、スタッフの顔を見て小さくニヤッとされています。 そして、指相撲でスタッフが勝つと、悔しそうな表情をされます。右利きの方なのですが、なぜか左指の方が力強く、指の使い方が上手いのでなかなか勝つことができません。 指相撲をしている時は、表情の変化がよく見られて指にもしっかり力が入っています。その力のおかげなのか、ご自身でお箸を持たれて、 食事を召し上がられています。
(2024年5月2日)
第33回【介護施設でのおすすめの手作業5選】
「介護施設でのおすすめの手作業5選」
今回は、利用者さんと一緒に行える手作業を5つ紹介したいと思います。ここでは、利用者さんに、お願いすることを、 『お手伝い』や『レクリエーション』と書かずに『手作業』と書いています。『お手伝い』だと介護スタッフの手伝いをする 利用者さん。という関係性になってしまうため、一緒に生活をする上で助け合っていきたいという想いで避けています。 『レクリエーション』のように楽しみながら、取り組んでいただきたいとは思っていますが、利用者さんの役割に していきたいという想いがあり、レクリエーションという表現も避けています。 取り組むには、難易度の高いものもありますが、少しでも参考になれば良いなと思っています。
①おしぼりたたみやタオルたたみ
「何かすることないか?」「手伝えることあったらするから言ってね」とよく声をかけてくださる方がいらっしゃいました。 何かしていただけることで、役割になり、少しでも充実した生活にならないか。取り組みやすいことはないかとスタッフ同士で 話をして、タオルを畳んでいただくのはどうだろうかと言う話になりました。タオルたたみは、指先を動かす運動にもなり、 脳への刺激にもなるのではないか。と言う意見から取り組み始めました。初めはスタッフと一緒にたたんでいたのですが、 そのうち「あんた、他にすることあるやろ?やっとくよ」とお任せするようになり、ご自身の仕事のように「タオルたたもうか?」と 声をかけてくださるようになりました。 「何か手伝うことはない?」と利用者さんがおっしゃってくださる時はありませんか?きっと「忙しそうだし、何か私にできることは ないかな?」「誰かの役に立ちたい」「してもらってばっかりで、何もできなくなってしまった」「暇だし、何か仕事が欲しい」 他にもいろんな想いがあると思いますが、こういった気持ちから声をかけてくださっているのではないかなと思います。 スタッフも何かしてほしいとは思うけど、何をしてもらったら良いんだろうか。お願いしても良いのだろうか。 見守りが必要で、お願いしている時間がない。という思いもあると思います。そんな時、食事の際に使うおしぼりや、 洗濯物のタオルなどを利用者さんにたたんでいただきます。おしぼりや、タオルを畳んだりするのは、怪我をする危険もなく、 取り組みやすいです。こういった手作業から依頼すると、どなたでも取り組んでいきやすいです。たたんでいただく前には、 必ず、手指の消毒を行っていただきます。簡単な作業ですが、利用者さんにとっては指を動かす体操になります。そのため、 着替えのボタンをとめる動作などの細かい動作の維持・向上にもつながると思います。
②縫い物
僕は職場で履いていたズボンのポケットが破れたことがありました。破れてしまったため、ズボンを履き替えると「どうしたの?」 と聞いてくださる利用者さんがいらっしゃいました。ズボンのポケットに指を入れて「破れました」と伝えると、笑って、 「針と糸持っておいで」と仰ってくださいました。お渡しすると、すぐに縫ってくださり、すごく手際も良く綺麗に縫って くださいました。話を聞くと「洋裁だけど、昔してたの。息子もよくズボンを破いて帰ってきたから、できるのよ。懐かしいわ」 と笑っておられました。今でも大切にそのズボンを履かせていただいています。利用者さんの中には裁縫が得意な方は いらっしゃると思います。伸びたズボンのゴムを通していただいたり、破れた部分を縫っていただいたり、ボタン付けお願いしたり、 古くなったタオルを雑巾にしていただいたりしています。 縫い物が得意な方がいらっしゃれば、縫い物をしていただくと手作業になります。指先の細かい作業なので、集中力も必要になります。 身体の色んな機能を刺激するので縫い物が得意な方には行っていただきたいです。針を糸に通す作業は難しい方もいらっしゃるので、 事前に準備しておくか、その都度スタッフが行うと「私にはできない」とおっしゃることもなく、スムーズに行えると思います。
③食器の拭きあげ
食後の食器を洗った後の食器は、置いていても乾きますが、食後のゆっくりした時間が退屈に感じられたり、落ち着かなくなる方も 少なくありません。しかし、食後はスタッフも、利用者さんお一人おひとりとゆっくりお話することが難しい時間だと思います。 そんな時に食器の拭き上げ作業を利用者さんと一緒に行っていました。数人の利用者さんと一緒に行えて、ゆっくりと お話しもできると思います。人は一緒に何かをすると、仲良くなれるようで、普段あまりお話しない利用者さん同士でも、 一緒に作業をすることで、話すきっかけになったり、共通点ができたりと、良い関係を築くことができると思います。 食器の拭き上げ作業は、簡単でいろんな方にお願いすることができるんじゃないかなと思います。そして、お一人おひとりの 指の力や、細かい作業が得意かどうか、目が見にくくなっていないかも見えてきます。拭き方でなんとなく性格が見えたりもするので 色んな視点で一緒に行うと面白い作業だと思います。
④園芸
ある夏の日、施設の庭に雑草が生えていました。背も高く、量も多かったのですが利用さんが「この草なんとかしたいな」と 仰ってくださり、そこからみんなで草刈りをすることにしました。夏の終わり頃だったのですが、暑い日もあり、1日20分ぐらいで 少しずつ草むしりを行いました。1ヶ月ほどで綺麗になり、みんなで「意外と広かったんやなぁ」と笑っていました。 「さぁ、何を育てようか。せっかく綺麗になったんやから、何か育てたいな」と話しておられました。みんなで、色々考えても なかなか答えが出ず・・・。「じゃあ、何が食べたいですか?」と聞くと「いちご!さつまいも!ぜんざい!」と食べたいものは たくさんあるようで、すぐに意見が集まりました。あずきを育てた方がいらっしゃって、簡単にできるようだったのと、時期的にも ちょうどよかったので、小豆を育てることになりました。利用者さんと水やりをして、収穫をして、殻剥きも行いました。 利用者さんは「早く美味しいぜんざいが食べたいな」と同じ目標に向かって、楽しんで作業に参加してくださっていました。 収穫した小豆は、利用者さんと一緒にぜんざいを作って食べました。草むしりから始まり、小豆を育てて、ぜんざいを作るまで 利用者さんと一緒にできた経験はとても楽しかったし、イキイキした毎日を送ることができたと思います。 庭があって、園芸や畑ができる施設もあれば、ベランダにプランターをおくことのできる施設もあると思います。 プランターだと育てられる植物や野菜の種類は、選ぶ必要がありますが、育てることで楽しみや、やりがいができることが 大切だと思います。園芸を始めると、毎日の水やりが日課になります。そして、天気予報を気にして、室内に入れてあげようか考えたり、 元気がなければ、肥料をまくことも考えます。園芸クラブを作るなどして、季節によって植えたいものを調べたり、探したり、 時にはお店に行って、野菜の苗や植物の種を見に行くことで、育てたい野菜や植物を見つけることができたり、育てるイメージも 湧くので楽しいと思います。そして想像することや、色んなものを見ることで良い刺激になると思います。施設の中で、なかなか 季節を感じることは難しいです。しかし、外に出たり、野菜や、植物を育てることで季節を感じることもできるんじゃないかなと思います。自分達で育てた野菜は格別で、野菜が苦手な利用者さんも「美味しい」と召し上がられます。
⑤調理
利用者さんに包丁を持っていただくのは、危ないんじゃないかと思うかもしれませんが、長年、台所に立って 調理をしてきた利用者さんの包丁さばきはお見事です。手続き記憶があるため、身体で覚えた記憶はなかなか忘れることが ないからです。一緒に調理をしていても「あんたの包丁の使い方見てたら怖いわ。包丁、貸して」と綺麗に、手早く切って くださいます。僕の方が、包丁の使い方が危ないなと感じます。 調理を利用者さんと一緒に行うのは、難しいと感じるかもしれません。僕が、今まで利用者さんと調理をしてきて一番簡単なものは、 ホットケーキじゃないかなと思います。トッピングのフルーツをスタッフが切れば、材料を混ぜて焼くだけだからです。ダマに ならないように気をつけたり、ホットプレートを使うので火傷に注意しながら焼くことで、調理をしている実感がわきます。 調理の工程を考えたり、火傷に気を付けて、焼き加減を見たりすることで、脳を働かせることができます。そして、腕を動かし、 ひっくり返す時の失敗しないようにする緊張感やうまくできた時の達成感も良い刺激になるんじゃないかと思います。 うまく焼けた時の利用者さんの嬉しそうな表情は忘れられません。ホットケーキを作ることができれば、たこ焼きを作ることもできます。 その時には、食材を切っていただける時間を作れたら良いなと思います。たこ焼き作りは、着る食材も多くなく、工程も簡単なため、 行いやすいです。食事作りは、利用者さんとワイワイ作ることができるので、普段は食事量の少ない利用さんでも楽しみながら 食事ができて、普段よりも、たくさん召し上がられます。食事作りで気を付ける点は、衛生面です。きちんと消毒と、調理用の手袋の 着用が必要です。調理は、お願いするには難しいこともあるかもしれませんが、お皿に取り分けることからお願いしてみると 良いと思います。お願いしていないから、利用者さんの能力に気づけていないだけで、利用者さんはスタッフよりも、人生経験が長く、 好きなことや、得意なことを活かせる場面は多いんだと思います。 ⑥洗濯物 洗濯物を干したり、畳んだりする作業を利用者さんと行います。入浴後や更衣したの衣類の洗濯物を干していただいたり、 干した洗濯物を畳んでいただく作業です。利用者さんは施設に入所される前にはご自身で行われていた方もおられると思いますので、 多くの方に協力していただける手作業だと思います。洗濯物を干す際には、しっかりと生地を引っ張ってシワにならないように 丁寧に一つひとつ行ってくださいます。数人の利用者さんが行ってくださると「何してるの?」と他の利用ささんも一緒に 参加してくださることが多いです。手作業とはいいながらも、家事になるので「今まで散々してきたから嫌やわ」と断る 方もいらっしゃいます。断られると寂しいし、心が折れそうになることもあると思います。そんな時は、快く引き受けて くださる方を見つけて、1人2人と少しずつ手作業をしてくださる方を増やして、輪を広げていくことが大切だと思います。 晴れた日には、外やベランダで洗濯物を干すのも良いと思います。陽の光を浴びることで、体内時計をリセットできたり、 免疫機能を高めたり、ストレスの軽減や精神を安定させる効果などがあります。他にも日光を浴びると色々な良い効果があります。 日光を浴びる時間がとれるようにする取り組みとしても、洗濯物干しを行ってみることをお勧めします。 手作業は、身体を動かすことだけが目的ではありません。利用者さんが、施設に入るまでにやってこられた日常生活を、少しでも 続けていけるように、支えていけたら良いなと思っています。それは、家事でも、趣味でも、仕事だったことでも、その方の 得意や、好きを活かして、その手作業で、利用者さんが「誰かのためになっている。今日も自分は誰かの役に立った」と思えることで、 社会的欲求、承認欲求、自己実現の欲求が満たされるんじゃないかなと思います。 利用者さんにお願いするよりも、スタッフがする方が早くできたり、丁寧にできることもあると思います。(僕よりも丁寧に作業を される利用者さんはたくさんおられますが)それでも、利用者さんに行ってもらう理由は、利用者さんに「ありがとう」と言って もらえる日常よりも「ありがとうございます」と伝えられることの多い日常をつくっていけるように、関わっていきたいからです。 利用者さんが、普通に生活するために介護士は存在するんだと思います。利用者さんの中には認知症の方、身体に麻痺があったり、 動かしにくかったり、車椅子を使用しておられたりもします。今回のおすすめ手作業は、利用者さんの能力を知らないと ヒヤヒヤすると思います。しかし、普通の生活を送っていただくためには、普段から利用者さんの身体能力を見極める目も必要です。 スタッフが利用者さんの行動をどこまで見守れるか、どこで介助するのかの視点も大切だと思います。お一人おひとりの身体能力や、 得意や好きを発見できると、どんなことをお願いしようかワクワクできる毎日を過ごすことができると思います。
(2024年3月27日)
第32回【介護職員が入浴介助で気を付けること6選】
今回は私が気にかけている「入浴介助のポイント」を6つ紹介したいと思います。
1.体調の確認を行う。
入浴前には、本人への体調の確認をし、顔色が悪くないか、普段と表情に変化はないかを確認し、 必ずバイタル測定を行います。体温、血圧、脈拍など、必要であれば血中酸素濃度を測ります。 今まで、大事に至ったことはありませんが、朝から熱がある。少し血圧が高い。などの理由で、入浴を中止したり、 シャワー浴に変更することがありました。体調の変化は、目にみえるものだけではないので、入浴前に バイタル測定を必ず行うことが大切です。 普段の血圧と比べて、高い時や低い時、熱がある時などは、看護師にまずは相談するようにしています。 看護師が常にいない施設もありますので、自分だけで判断せず、判断できないときは、無理せずに入浴を 中止することも考えます。普段からの血圧が平熱が高い方や、低い方もいらっしゃると思います。 その方達は、どのくらいなら入浴してもいいのかを看護師や医師と相談して、決めておくといいかもしれません。
2.衣類を準備する。
私は、できるだけご自身で着たい服を着て欲しいと思っています。ある日、お風呂に行く時に、利用者さんと 一緒に服を選んで、どの組み合わせにするかなど話していました。すると、普段あまり着ておられない 服を選んでおられました。入浴後に、職員さんから「あら、珍しい服。前はよく着てましたね。素敵ですね」 と声をかけられて恥ずかしそうに、嬉しそうにされていました。その後、その服はお気に入りのローテーションの 仲間入りをしていました。利用者さんと一緒に着たい服を選ぶことができて、よかったなと思う経験がありました。 お風呂の準備をする時など、利用者さんと一緒に衣類を選ぶようにしています。理由の1つは『今からお風呂に行く』 と認識していただくためです。心の準備ができていないのに、急にお風呂に連れて行かれると、 誰でも、拒否したくなると思います。そして、お風呂に入るのはいいけれど、着替えの準備があるかも分からないと、 お風呂から出た後はどうするのかと不安になり、服を脱ぐことはできないと思います。「お風呂に入らない。入りたくない」 と言う気持ちになってしまう原因の一つなんじゃないかなと思います。一緒に着替えを準備することで、心の準備もできて、 着たい服も用意することで、安心して浴室に向かうことができると思います。もう1つの理由はご自身の好きな衣類、 今の気分にあった衣類、できれば気分が上がる衣類をご自身で選んでいただけるからです。衣類には、その方の趣味や 嗜好や性格が出るのでどんな服を着ておられるかで、なんとなくその方の人柄が見える気がするからです。ご自身で 選ぶのが難しい方でも、服の組み合わせや、どんな服をよく着ておられたかなど、ご家族に聞いたり、できるだけ 同じ服ばかりの着回しにならないように気をつけることが大切だと思います。
3.プライバシーへの配慮
入浴を断られることが多い利用者さんがいらっしゃいました。浴室までは入ってくださるのですが、 衣類を脱ぐことに抵抗があったようで、何度も断っておられました。そんな時にいつもより、多めのタオルを 持っていき、手すりにかけて「タオルで見えないようにするので」と伝え、目を合わさないようにしてました。 すると、少しづつ脱いでくださいました。浴室に入るまでには肩からタオルをかけて、腰にバスタオルを巻いて おられましたが、髪の毛も身体も洗っておられました。その日は湯船に浸かられることはありませんでしたが、 徐々に拒否はなくなり、最終的には湯船に浸かってくださるようになりました。 入浴介助では、利用者さんは、職員に裸を見られてしまいます。きっと、見られたくない・恥ずかしい。 いろんな思いがあると思います。同性介助ができればいいとは思いますが、難しい施設は多いと思います。 できるだけ、恥ずかしいと思わせないように、ご自身で着脱ができる方の時は、衣類を脱がれる前に 手すりにタオルをかけて、脱いだ後にタオルで身体を隠すことができるように準備しています。そして転倒されないか、 急に立ち上がられないかを見守りしながら衣類を畳んだりして、着脱している様子を凝視しないように配慮するように 気をつけています。
4.転倒に注意する
普段は見守りにて歩行されている方がいらっしゃいました。入浴の時は、脱衣場から浴室に入る時に「怖いわ。 転けへんかな」とスタッフの手を握り、ゆっくりと入る方がいらっしゃいました。怖いと慎重になり、 手にも力が入ってしまうんだなと思いました。声かけをして、手すりを持っていただきながら、 反対の手を支えると、ご自身のペースで浴室に移動しておられました。 浴室は濡れるので浴室内を移動する時には、普段以上に注意が必要です。利用者さんも滑らないか不安で、 緊張しておられるため、普段より身体がかたいこともあります。歩行に手引き介助が必要な方は皮膚に 直接触れてするため、持つ位置や、指で腕などを握ってしまわないように、手のひらで触れるように 意識することを心がけています。 更衣の時にも、立ったまま着脱しようとする方もいらっしゃいますが、椅子を用意して、手すりに掴まれる 安全な場所で着脱介助を行うように心がけています。
5.洗髪と洗身をする
入浴の時に、寒がりな利用者さんがおられました。かけ湯のシャワーも常温くらいの温度でないと「あつい!」と おっしゃる方でした。洗髪の時などにシャワーをとめると「寒い!」とおっしゃっていました。シャワーの温度も ぬるいからだと思います。その後も湯船の温度が40℃程度あったので湯船に浸かるのも熱かったんだと思います。 僕は、できるだけその方が「寒い。熱い」と不快に感じず入浴できるように、常温のシャワーから、徐々に 温度を上げていき、かけ湯2時間をかけました。その後もタオルを背中にかけて、シャワーを肩からかけながら、 頭と身体を洗いました。うまくいかなかったこともありますが、お風呂から出るまで「熱い、寒い」と おっしゃらなかったこともありました。不快な思いをせずに入浴していただけるように配慮するのは 難しいですが、何が嫌なのかがはっきりしていれば対応できると思います。 利用者さんの身体を洗う前に、かけ湯をする時は、心臓から遠い足先や、手でシャワーの温度を確認していただきます。 体が冷えていると、職員はぬるく感じていても、利用者さんは熱く感じることがあるからです。確認していただいた後も、 急な温度変化によって、心臓に負担をかけないために徐々に身体の外側の心臓に遠いところから、お湯をかけていきます。 介護を始めた時は、耳にシャワーが入らないようにするのに苦労しました。手で押さえても入っているような気がして、 手の位置もなかなか定まりませんでした。髪の毛を切りに行った時に、意外と手を添えてるだけだな。流してシャワーが 当たらないようになってから、手を離しているんだなと直接聞くことができずに、考えながら髪の毛を洗って もらっていたのを覚えています。 他人の髪の毛を洗うのは難しく、初めは苦戦しました。力加減が難しく「もうちょっと力入れて」と言われたことも ありました。腹の指を浸かって洗っていましたが、力を入れて利用者さんに触れることなんてなかったので、 怪我させてしまわないか、初めは不安でした。しかし、自分で髪の毛を洗う時に、どのくらいの強さで洗っているのか、 散髪に行ったときに、どのくらいの強さが気持ちいいのかを考えていました。そして、自分で髪の毛を洗う時と同じくらいの 強さで洗わないと、気持ち悪いことに気づきました。そこからは、少し力を入れても怖くないようになり、利用者さんからも 「もうちょっと力入れて」と言われなくなりました。 人の髪の毛を洗う難しさはありますが、自分が洗われたら気持ちいいのか、どうされたら不快に思うのかを考えて 洗髪しています。爪は短く切って、爪を立てずに指の腹で洗うと利用者さんを傷つけることはないと思います。
6.皮膚状態の確認
利用者さんの身体を見るタイミングは、なかなかありません。入浴の時には、全身を確認するようにしています。 お風呂が嫌いで、家でもあまり入っていなかったという方が、入所されました。入所後は、お風呂に入って くださったのですが、身体を見せていただくと、かき傷や発疹があり、すぐに看護師さんに薬を塗るなどの 処置をしてもらったことがありました。その後は、入浴回数も増えて、体も綺麗になったのですが、 更衣する時や、トイレの時などでもなかなか見せていただけないところがあると思います。 お風呂の時は、自然と裸になるので、その時に身体の変化や、傷やアザなどがないか、確認できる タイミングだと思います。 最後に、室温は季節や利用者さんの体感温度によって少し変えますが、入浴や更衣の時などの時は、 だいたい24℃前後が適温だと言われています。服を脱ぐため、利用者さんが、寒いと感じない温度に 設定することを心がけています。 脱衣室だけでなく、浴室の室温調整も必要です。お風呂に暖房設備がない場合は、入浴前に熱いシャワーを 出し、浴室だけでなく、床や椅子を温めると快適に入浴することができると思います。 入浴前に寒いと感じず、入浴後は、気温差でヒートショックを起こさないように気を付けることが大切だと 思います。
(2024年3月12日)
第31回【ほんとにあった介護現場のほっこりする話】
「綺麗になりたい」
普段から美意識の高い利用者さんがおられました。オシャレな服をたくさん持っておられ、美容院では髪の毛を毎回染めてこられます。
「私はいつでも恋をしたいのよ。彼氏募集中」と笑ってお話されています。そんな利用者さんは、お薬を飲む時でも美を追求されます。「この薬はなんのお薬?綺麗になるお薬?」と聞かれます。
「はい。美は内面からくるものらしいですよ。腸から綺麗になりましょう」と調整剤をお渡しすると、
「私は、すぐに綺麗になりたいのに!」とわざと少し残念そうな顔をして見せて笑っておられました。
気さくな利用者さんにいつも元気をもらっています。笑顔の絶えない明るい方は素敵だなと思います。
「新しいお友達?」
利用者さんと、散歩を兼ねてゴミ拾いに行った時に、近所の公園で子供がお母さんと遊んでいました。
子どもの好きな利用者さんが、その子に近寄り「あなた、いくつ?」と聞くと、子供は恥ずかしそうに、指を『2』にして見せてくれました。
それを見た利用者さんに2歳だということをお伝えすると「2歳なの?私、97」と笑顔で返答されました。
お母さんが「お元気ですねぇ。こんな歳の差のある方と出会う事なんてなかなかないですねぇ」とびっくりしておられました。
「ほんとねぇ。95歳も離れてるのね」と笑っておられました。最後は95歳の歳の差のお二人が、握手して手を振ってお別れしました。
施設に戻ってからも「可愛かったねぇ。また会えるかな。また散歩に行きましょうね」とおっしゃっていました。
「将棋の藤井名人のことが心配」
将棋の藤井名人が高校生の時からのファンで、対局に勝つたびに「若いのにすごいね。まだ学生で、将来が楽しみね」と
自分のことのように喜んでおられました。そんな中、新聞で高校を自主退学をした記事を読み「この子は高校辞めて、大丈夫かな?将棋の道だけにするのは大変かもしれへん。高校だけはちゃんと卒業してからやったらあかんかったんやろか」とそこからは心配されて、藤井名人の対局がある度にソワソワされていました。
将棋が好きなわけでもなければ、ルールも知らないとのことで、対局を見たりはされないのですが「まだ結果出てないか?結果は明日か」と聞いておられました。
次の日に新聞を見て「あーよかった。勝ちやってんなぁ。ドキドキするわ」と目に涙を浮かべながら記事を読んでおられました。
安心されてからは「凄いなぁ。高校辞めるって決断して、あの時はどうなるかと思ったけど」と話されていました。
対局がある度にニュースや新聞を気にしておられます。
「歌手」
いつも歌の本を持ち歩いておられる利用者さん。歌が大好きで、音楽番組を見ていると一緒に歌っておられます。
そんな利用者さんですが、アカペラでも歌えるんです。いつも持ち歩いている歌の本から得意な歌のページを開き「これは〇〇さんの歌でな、私よく歌ってたの」と、近くに座っている利用者さんに話しかけておられました。
「みなさんで歌いましょうか?」と提案すると「そうね。歌いましょう!」と大きな声で歌われます。
最後はみんなで拍手をして終わるのですが、歌が大好きなその利用者さんは、ページをめくり、次の曲を探されます。
そこからは、立ち上がりお一人でフルコーラス歌われます。周りからは「上手ねぇ。これだけ歌えたら気持ちいいだろうねぇ」と拍手を受けると、恥ずかしそうに「汗かくわぁ。恥ずかしい」と言いながら、すぐに席に座られるのですが、また立ち上がりいろんな曲を披露してくださいます。
男性職員とのデュエットでは、腕を組んカップルのように歌っておられます。
「嬉しい冗談」
帰宅欲求や介護拒否のある利用者さんがおられました。衣類汚染をしていても、トイレの声かけには拒否され介入もさせていただけず・・・。
入浴も「家で入るからここでは入らない」と強く拒否されていました。
根気強く関わり、少しずつ施設に馴染まれて、トイレの介入もさせていただけるようになりました。
使用済みのパッド類は新聞紙に包んで捨てるようにしているのですが、そんなある日、その利用者さんのトイレの介入をさせていただけました。
汚染パッドを新聞紙で包んでくださっていました。(新聞紙に包むことで、消臭効果があります。トイレには新聞紙が置いてあり、パッドが汚れて、破棄する際に使っています。基本的には、職員が行うのですが、職員が包んでいるのを見て、ご自身で包んでくださる方もいらっしゃいます。)
お礼を伝え、預かろうとすると「はい。お土産」と悪戯っぽく笑って、手渡してくださいました。入所当初は、なかなか冗談も
言ってくださらず「ほっといて」とおっしゃる事の多い方でしたが、少しずつ心を開いてくださり、冗談を言ってくださるようになりました。
利用者さんが、心を開いてくださったんじゃないかなと感じられる瞬間はとても嬉しいです。
「あんこの威力」
ある日、利用者さんとぜんざいを作ろうと計画していました。昼食後の眠たい時間帯でした。
「何を作るの?」と話している利用者さんもいらっしゃれば、ウトウトと居眠りしている利用者さんもいらっしゃいました。
「今からぜんざいを作りましょう」とお話しすると「あんこ?」と嬉しそうに質問される利用者さんがいらっしゃいました。
その声にピクっと反応される居眠り中の利用者さん。「そうですよ。このあんこを使ってぜんざいを作っていきたいと思います。みなさんご協力お願いします」と声をかけると『あんこ』の言葉に目を覚まされた利用者さんが「私、あんこ大好き。もうお腹が空いてきた」と腕まくりをして参加してくださいました。甘い物の原動力って凄いなと驚きました。
みなさん手慣れておられ、手際がよく、職員は、ほとんど何もすることなく、出来上がってしまいました。
利用者さんが作ってくださったぜんざいは、甘くてとても美味しかったです。
(2024年2月27日)